
若手社員が働きやすい環境を整備
3Kというネガティブなイメージを払拭
建設業界には、「3K」(きつい・汚い・危険)という労働環境に対するネガティブなイメージが根強く残っている。建設業界は人材不足が深刻な問題となっており、特に若手人材の確保が難しい状況にある。その要因の一つに挙げられているのが、3Kだ。
「人口減少や高齢化に伴う人手不足に加え、3Kというネガティブなイメージが付きまとい、当社も若手人材の獲得に苦戦している状況でした。こうした現状を打開するべく、当社の代表取締役である後藤茂之が注目したのが、DXです。DXによってアナログのプロセスが主流である建設現場の業務改善と生産性アップを図ることで、若手社員が働きやすい環境を整えられるのではないかと考えたことがきっかけです。会社を変えていくための一歩として、DXの取り組みを始めました」と後藤組 経営管理部 部長 笹原尚貴氏は振り返る。
こうした背景の下、後藤組は2021年に「DX戦略」を策定し、社員一丸となって“全員DX”の実現に向けた挑戦を続けている。「全員DXとは、一部の社員だけが取り組むのではなく、現場の社員を含めた全員が主体となってDXに取り組んでいくという考え方です。これを実現するために行っているのが、全社員がアプリ開発に挑戦するという取り組みです。現場で働く社員一人ひとりが、自身の業務を改善するために必要だと考えるアプリを自ら開発しています」(笹原氏)
4年間で3,000件を超えるアプリを開発
社員のさまざまアイデアが業務を改善

笹原尚貴 氏
アプリ開発には、サイボウズの業務アプリ作成ツール「kintone」を活用している。kintoneは、プログラミングに関する専門的な知識がなくても、ノーコードで業務アプリを作れることが特長だ。「情報システム部門を持たない当社にとって、ITの専門家がいなくても、現場で働く社員自身が業務に必要なアプリを簡単に作成できる使い勝手の良さが導入の決め手となりました」と笹原氏。
現場内で危険が潜んでいる場所や作業を洗い出して事前にトラブルを防ぐ「危険予知活動」に関するアプリ、勤怠管理のアプリ、人事部門が活用する新卒採用管理アプリ、営業担当が扱う顧客管理アプリなど、実際に社員のさまざまなアイデアが具現化されてきた。「社員が作成したアプリの総数は4年間で3,000件を超えています。アプリの活用によって蓄積されたデータを基に、Googleのダッシュボード作成ツール『Looker Studio』で可視化や分析をしたり、⾃社開発したAIモデルと組み合わせたりするなど、多彩な発想によるデータ活⽤も広がっています。また、アプリの活用で業務効率化につながり、残業時間が約20%削減し、⽣産性が約38%アップするといった⼤きな成果をもたらしています」と笹原氏はアピールする。

後藤組では、内製的なIT人材の創出に向けて、社内のリカレント教育にも力を入れている。年に一度全社員が集まって自作のアプリをプレゼンする「DX大会」、kintoneのアプリ開発やダッシュボードの作り方といったDXに関するスキルを学ぶ「DXワークショップ」、後藤組におけるIT人材スキルを測定する社内試験「社内認定資格制度」などさまざまな教育体制を用意する。社内教育の仕組みを通じて、デジタルスキルを向上し、社員が自ら課題を見つけて解決する能力などを養う。
DXを推進したいと考えてはいるものの、DXがなかなか進まないといった課題を抱える企業は少なくない。笹原氏は「トップがDXの必要性を強く認識し、社員に対して何度も根気強くその重要性を伝え続けることが不可欠です。加えて、一部の担当者だけでなく、現場の社員を含む全社員を巻き込み、主体的にDXに取り組む体制をつくることが重要です」とアドバイスする。
同社では、DXの取り組みを通じて新卒者の定着率が向上するなど、良い変化も起きているという。若手社員が働きやすい環境づくりをこれからも継続していく。「今後は、さらにデータ・ドリブンを推進していきたいと考えています。また、生成AIなどの最新技術を取り入れ、変化する時代の流れに柔軟に対応しながら、業務変革を進めていきたいですね」と笹原氏は展望を語った。


DX推進を加速させるためには
トップが率先して行動

松尾逹磨 氏
多くの企業でDXの実現に向けた取り組みが加速しているものの、想定していたように進捗せず、難航しているケースは少なくない。順調に進む企業と難航する企業の差は、どこから生まれるのだろうか。その要因の一つとして挙げられるのが、経営層のDXに対する理解だ。DXに取り組む上で変化を恐れず新しいものを受け入れる姿勢を持っているか、現状の課題を把握して適切な方向性を示すDX戦略が立てられるかなど、経営層がDXに関して正しく理解をしていれば、企業のDXは順調に進められるだろう。それを体現している企業が、山口産業だ。

坪上竜也 氏
山口産業の代表取締役である山口篤樹氏は、自らがデジタル技術に関する情報収集や早期導入を推進するなど、DXに積極的な姿勢を示している。「当社は、トップが率先して失敗を恐れることなく挑戦する姿勢を発信しています。新たな技術への理解や意思決定も早く、当社はこれまで数々のDX推進に向けた取り組みを行ってきました。経営者が率先して新しい取り組みに挑戦する姿勢を示すことが、組織のDX推進の加速につながっていくといえるでしょう」と話すのは、山口産業 DX推進室 室長 兼 製造部 管理課 課長 松尾逹磨氏だ。
同社は、2024年に「経営ビジョンに基づくDX計画」を公表している。その中で、データとデジタル技術を活用することで、製品やサービスなどのビジネスモデルの変革を促す「山口産業DX戦略」を提示した。山口産業DX戦略には、「DXによる業務効率化と業務プロセスの改革」や「DX人材教育による組織力強化」といったロードマップが定義されており、これを基に戦略を立て、DX戦略実現に向けてさまざまな取り組みを進めている。


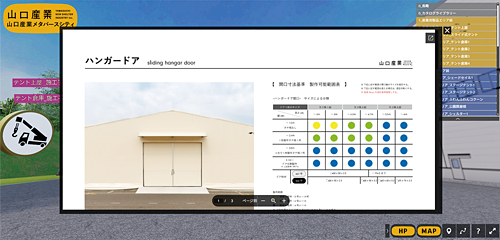

自社膜構造製品を中心としたメタバースシティを製作。主力製品であるテント倉庫などは実物に近い再現性を実現している。
業務改善を継続的に実行して
社員の意識改革にもつなげる
山口産業では、これまでDX推進に向けて数多くの業務改善を実施してきた。基幹システムと周辺システムの刷新をはじめ、HP上で製品サイズや仕様を2Dでシミュレーションできるシステムの実装など業務の効率化を図っている。「年間60件前後の業務改善を継続的に行っています。社員からも業務改善提案を提出してもらい、主体性を持たせることで、DXに対する意識改革にもつながっています。業務改善の仕組みが整えられていることも当社の強みです」(松尾氏)
また、同社が業務効率化と業務プロセス改革を実現するために取り組んでいるのが、「山口産業メタバースシティ」の製作だ。メタバース空間にテント倉庫をはじめとする同社の膜構造製品などが実装されており、その場で実物を見ているかのようなリアルな体験ができる。「テント倉庫などの膜構造は建築物であるため、お客さまに実物を見せる機会が限られているという課題がありました。こうした課題を解消するため、お客さまがどこにいても商品を見られるメタバースシティの製作を約2年かけて進めました。BIMデータを活用し、リアルに近い空間を再現していることもポイントです。今までの営業の在り方を変える商談ツールになるのではないかと考えています」と山口産業 DX推進室 坪上竜也氏はアピールする。
山口産業では、DX人材の育成にも注力しており、DX人材育成プロジェクトを立ち上げ、教育体制を整えている。「DX推進を行う上で、DX人材を増やしていくことが重要です。各部署のキーマンを育てていくことで、組織力の大幅な向上が期待できるでしょう。併せて、当社では、社内全体のITリテラシーを向上させることに重きを置き、勉強会や講習会などを実施しています」と松尾氏は説明する。
今後も同社は、ビジネス環境の変化に柔軟に対応しながら、DX戦略実現に向けて取り組みを加速させていく。



機器の稼働状況を可視化し
安定操業につなげる
鶴見製紙がDX化に取り組み始めた背景には、トイレットペーパー製造を担う製紙工場ならではの悩みがあった。鶴見製紙 業務部 部長の刈谷大吾氏は「トイレットペーパーは24時間体制の連続操業で製造します。そうした中で機器トラブルによって製造が停止すると、当然生産ロスにつながるのですが、以前の当社はこの突発的な機器トラブルが頻発しており、安定操業が困難な状況でした」と振り返る。24時間操業であるが故に、深夜にメンテナンスが行える従業員を電話で呼び出すこともしばしばあったという。「休日出勤も常態化するなど、従業員の身体的、精神的な負担が非常に大きい状態でした。そうした機器の問題と、従業員の働き方の問題を解決するために10年前ごろから取り組み始めたのが、IoT化の推進です」と刈谷氏。
鶴見製紙では、生産設備の各機械にPLC(Programmable Logic Controller)を取り付け、稼働状況などのデータを取得できるようにした。またメンテックの製紙プロセス最適化システム「SmartPapyrus」を導入し、抄紙工程の操業情報をモニタリングすることで、抄紙機の操業情報を一元的に監視できるようにしたという。2020年には、もともと工場内で休憩所として使用していたスペースにPCやモニターを整備して機器の状態や生産状況を可視化できる環境を整備し、「中央監視室」としてリニューアルした。これらの取り組みによって、機器の予防保全が実現でき、トイレットペーパーの安定生産が可能になったのだという。

(左)刈谷大吾 氏
(右)中村俊介 氏

生産情報もデジタル化
働きやすい環境へと変革

こうした機器のIoT化の取り組みに加え、鶴見製紙では点検情報や生産情報のデジタル化にも取り組んだ。同社ではもともと、2005年ごろからApple子会社のClarisが提供するデータベース管理システム「FileMaker」を導入し、製造部の情報のデータ化を全社的に進めていた。しかし、FileMakerはカスタマイズ性が高い一方で開発や管理が属人化しやすいという課題も生じていた。
そこで鶴見製紙が導入したのが、サイボウズが提供する「kintone」だ。プログラミングの知識がなくても業務に合わせたアプリをノーコードで作れるkintoneで新しく点検情報や生産情報を管理できるアプリを作成し、FileMakerで管理していたデータを集約した。それに加え、物品購入の承認ワークフローなどもkintone上で行えるようにしたという。
鶴見製紙 製造本部 品質管理部 品質管理課長兼 仕上部 加工課長の中村俊介氏は「kintoneはコメント機能が非常に便利です。当社は前述した通り24時間工場が稼働しているため、日勤と夜勤があります。そうした環境ですと、書類確認が必要な場合、申請者と承認者の勤務時間がかぶらないとオンタイムでの確認ができませんが、kintoneのコメント機能を活用すれば勤務時間がかぶっていなくても、kintone上で細かな確認ができ、スムーズに承認が行えます。当社は情報システム部門がなく、製造本部の私や業務本部の刈谷がIT関連の管理を兼任しているのですが、こうした兼任の担当者でも簡単にアプリが作れますし、リリースしてから現場の作業員からの要望を受けて、その場でカスタマイズすることも可能です」とkintoneの利便性の高さを語る。工場内にはiPadを常設しており、その場でkintone上のアプリに必要な情報を入力できるようにしているほか、従業員1人につき1台のiPhoneを支給しており、さまざまな場所からデータベースへの情報入力が行える環境を整えている。
このような機器のIoT化と生産情報のデジタル化の両軸によるDXに取り組むことで、いくつかの効果も生まれている。例えば、従業員の定着率の改善傾向が見られることに加え、若年層の採用活動も進んでいるのだ。刈谷氏は「現在では高卒人材の採用も進めています。過去の働き方ですと、高校を卒業したばかりの方は保護者から就職を反対されるような環境でした。そうした若い従業員が長く働ける環境に改善できたのは、DX化による効果だと思います」と語る。
また、鶴見製紙では現在、大手小売店のプライベートブランドのトイレットペーパーの製造も手がけている。こうしたプライベートブランドの製品は、品質が悪いとその企業のネームバリューを傷つけるため、品質管理は欠かせない。IoT化による機器の管理や、kintoneによる点検情報の管理が行えるようになったことで、品質管理の質も向上できているようだ。中村氏は「製造、販売、経営層の意思決定においてPDCAサイクルを回す上でもデータの活用は不可欠になっています」とデジタルツールの必要性を語る。
鶴見製紙がDX推進を成功した背景には、トップダウンによる方針決定が大きい。「経営トップの方針決定と、それに伴う潤沢な資本の投入がDX成功のカギになっています。情報システムの管理を担う私たち自身が製造現場を兼任しながらDX化を進めていますので、現場に近い感覚で改善を進めることができていることも、成功の要因としてあるでしょう。また定期的な社内勉強会も開催することで、ツールの使い方や情報リテラシーの周知に取り組んでいます。今後は生成AIを含めたAIの活用を視野に入れ、さらなるデータ活用に取り組んでいきたいですね」と刈谷氏は展望を語った。








